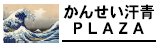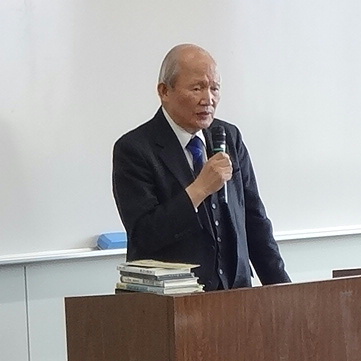「皇室典範」改正への段階案と論拠
京都産業大学名誉教授 所 功
実現可能な法改正を続行する
一昨年末の政府案に基づく「安定的な皇位継承に関する与野党協議」は、一年余りかけても纏まらず新年を迎えた。しかし、一月八日の「読売新聞」朝刊によれば、協議は「月内に再開する方向で調整に入った。夏の参議選までに、一定の結論を得ることを目指す」という。
もしそうであるならば、その「一定の結論」を受ける政府としては、与野党の大多数が賛成できる現実的な改正案を国会に提出して成立させ、それ以後一年ほどかけて次回の改正案を作成し成立させる努力を続けていく必要があろう。
ここにいう現実的な改正案は、第一として、皇族女子(内親王・女王)が結婚される際、㋑皇籍を離れる現行典範の原則を残すと共に、㋺皇室に留まることもできる例外を認める。ただ、㋺の場合、その夫と子供を皇族の身分とするか否かは、次回の改正案に先送りすることである。
また第二として、いわゆる旧宮家で男系男子孫の中に養子として皇族らしくなれる適任者があり、皇室(内廷、宮家)で養子を必要とされる場合、皇室に入れるようにしておく。ただ、その養子皇族の資格や序列(㋺との関係で変動)などの明文化は、次回の改正案に先送りすることである。
皇室と皇位の本質理解を共有する
こうして実現可能な法改正を進めようとする過程で、最大の論点になると予想されるのが、Ⓐ「皇統は男系」Ⓑ「皇位は男子」という先入観の再検討である。この二点を冷静に検証すると、歴史的・相対的な原則と認められるが、普遍的・絶対的な原理とは考え難い。その論拠を略述しよう。
現行の「皇室典範」は、第一条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定める。これは皇位の継承者を、ⓐ「皇統に属する男系」に絞るだけでなく、ⓑ「男系の男子」に限るものであって、いわゆる女系天皇を否定するのみならず、男系女子の女性天皇すら否認している。
しかし、皇室には古来「姓氏」(今なら名字)がなく、皇統には本来「男系・女系」の区別もない。ただ、古代中国より姓氏を有する皇帝中心の男系(父系)を絶対視する風習・法令が導入された影響もあって、わが国では男子優先の実例が多くなり、結果的に男系中心が原則のごとく理解されるに至った。それを明治以来の「皇室典範」で絶対的な原理と解して、女子も女系も排除したのは、行き過ぎといわざるをえない。
従って、現行典範のもとで確定された皇位継承は、「男系の男子」限定によって二代先まで進むことになろう。ただ、その先の在り方としては、歴史上に多かった「男子優先」(女子公認)を取り戻すことが妥当(穏当)だと思われる。
そのためには、現行典範の第一条にいう「男系男子」の原則を残しながら「男系女子」も(できれば女系男女も)例外として公認する法改正を、第三段階で実現させることが必要だと思われる。皇位継承者の必須要件は、「皇室で生まれ育って皇族の身分にあること」にほかならない。 (令和七年一月三十日)