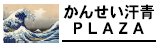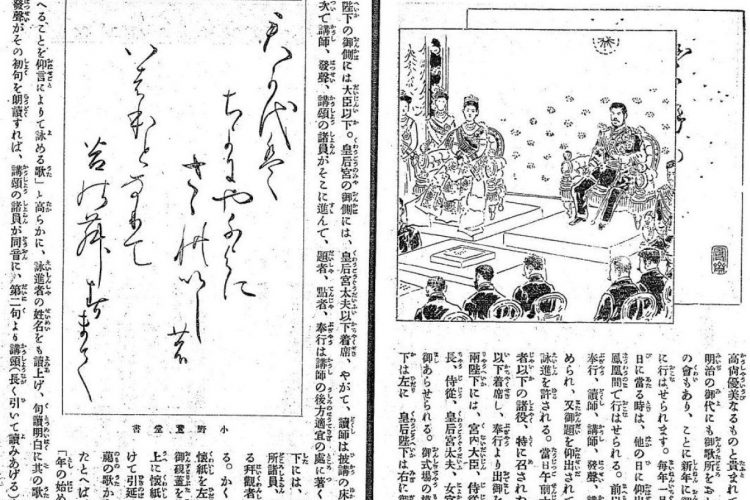歌会始の来歴とその意義
久禮 旦雄
新年恒例の歌会始の儀が、今年(令和7年=2025)も皇居・宮殿「松の間」で行われた。歌会始は例年、1月15日前後に行われていたが、今年は天皇皇后両陛下が阪神・淡路大震災30年追悼式典にご出席される関係で、1月22日の開催となった。また、今年は敬宮愛子内親王殿下が初めてご出席されたことも話題となった。
1 歌会始の次第
歌会始は、天皇皇后両陛下の前で、一般からの詠進歌、選者の歌、召人(天皇から特に召されて歌を詠む人、以前は高官・政治家が務め、その後文化人、最近では歌人が多い)の歌、続いて皇族の方々のお歌、皇后陛下の御歌、最後に御製(天皇陛下が読まれた歌)が披講される。天皇皇后両陛下のほか、皇嗣殿下をはじめとした皇族の方々や国務大臣、日本芸術会会員、詠進者、培聴者が列席する中での披講(歌の読みあげ)の様子は、毎年NHKで生中継されている。
当日は午前9時ごろから集合した参列者が、10時過ぎから入場し、一同が着席すると、歌会始委員会幹事が、選ばれた歌(預選歌)の懐紙が入った硯蓋をもって式場中央の披講席に進み、卓の上に置いて、席に戻る。この瞬間、式場は静まりかえる。NHKの中継はおおむねこのあたりからはじまることが多い。
10時30分になると、天皇陛下が皇后陛下とともに松の間にお出ましになり、続いて皇嗣殿下・皇嗣妃殿下、さらに愛子内親王殿下をはじめとした皇族の方々が続き、それぞれ着席される。侍従・女官がそれぞれ天皇陛下の御製、皇后陛下の御歌が入った御懐紙文庫を捧げ持って、両陛下の御前に進み、それぞれの御卓の上の小蓋の上に御懐紙を移し、戻って着席する。
式部官長が目する(目くばせする)と、読師(進行役)が披講の席に着き、硯蓋から預選歌の懐紙をとりだして左脇に置く。読師が講師に目すると、講師が披講席に着き、発声(1人)・講頒(4人)も続く。いよいよ披講が始まる。
披講は、講師が「年のはじめに同じく「題」、ということを勅(おおせごと)によりて詠める歌」と述べ(端作)、続いて披講する歌の預選者の都道府県と名前(姓と名の間に「の」を入れるのが慣例)が読み上げられる。講師は歌の各句をゆっくりと読み上げ、続いて発声が初句(最初の5文字)を節をつけて詠み、第二句以下を講頒が加わって詠み上げる。以下順々に披講が行われる。その後、皇族の方のお歌一首、皇嗣妃殿下(ひつぎのみこのみめ)に続き皇嗣殿下(ひつぎのみこ)のお歌が披講される。
皇后陛下の御歌の際には、それに先立ち読師が立って皇后陛下の御前から御懐紙を戴いて下がる。講師は「「題」ということを詠ませ給へる皇后宮御歌(きさいのみやのみうた)」と読み、披講が行われる。この時、宮内庁長官が先導して天皇陛下以外、皇后陛下も含めて一同が起立する。
最後の天皇陛下の御製に先立ち、同様に読師が懐紙を戴き、講師は「「題」ということを詠ませ給へる御歌(おおみうた)」と読み、披講が行われる。この時も一同は起立する。
御懐紙などが元に戻され、天皇皇后両陛下が退出なさると儀式は終了する。儀式全体として、読師が進行役とされるが、特に声を出して指示を行うわけではない。披講以外は終始沈黙のうちに、儀式が行われるのである(中島宝城「宮中歌会始」財団法人日本文化財団編『和歌を歌う 歌会始と和歌披講』笠間書院、坊城俊周「歌会始と披講」菊葉文化協会編『平成の宮中歌会始』NHK出版、所功「和歌の勅撰と歌会始」皇室事典編集委員会『皇室事典 文化と生活』角川ソフィア文庫)。
2 歌会始の来歴(1)-京都における和歌御会始の成立
歌会始の名称は大正時代以降で、それ以前は「和歌御会始」と呼ばれていた。いずれにしてもその始まりは明確ではない。新年に宮中で歌会が行われた古い例としては、鎌倉時代の貴族で、歌人としても有名な藤原定家の『明月記』の建仁2年(1202)正月13日条に、和歌所の歌人を中心として歌会が行われたという記事がある(ちなみに、定家の子孫である冷泉家では、現在でも京都御所近く、現存する最古の公家屋敷とされる冷泉家住宅において毎年正月中旬ごろに歌会始が行われている)。また、文永4年(1167)正月15日に「内裏御歌始」「和歌御会始」と称される歌会が行われている(『大日本史料』同日条)。しかし、後醍醐天皇が宮中の儀式の記録と復興を目指して著された『建武年中行事』には正月の歌会の記事はなく、断続的に行われていても、恒例の行事になっていたかは疑問視されている。一方、江戸時代初期の後水尾天皇が後醍醐天皇の遺志を引き継ごうとして記された『後水尾院当時年中行事』には正月19日のこととして「(和歌)御会始」の記事がある。
東大史料編纂所教授を務めた酒井信彦氏は、以上の事実から、南北朝時代から江戸時代にかけての間に、和歌御会始が恒例の行事となったと推測している。そして、応仁・文明の乱により衰微した朝廷において、むしろ文芸の機運が高まる中、毎月の歌会(月次歌会)が盛んになり、さらに後柏原天皇の文亀2年(1502)に披講を伴う正月の歌会が行われ、それが以後24年間毎年欠けることなく行われたことから、これこそが和歌御会始の成立としている(酒井信彦「京都御所における和歌御会始」前掲『和歌を歌う 歌会始と和歌披講』)。
また、慶応義塾大学教授の小川剛生氏は、『晴和歌御会作法故実』という史料に基づき、明応10年(文亀元年)に後柏原天皇が正月の月次歌会を独立して行ったのが歌会始の直接の起源と論じている(小川剛生「北朝和歌御会について -「御会始」から「歌会始」へ-」同『二条良基研究』笠間書院)。後柏原天皇の時代は、いわゆる「戦国時代」の前期にあたり、朝廷は政治的・財政的に衰微し、即位から21年後にようやく即位礼が行われるほどであった。そのころに、現在にも受け継がれる和歌御会始がはじめられていることは興味深い。
以後、何度かの中断をはさみながら、江戸時代の後水尾天皇以降、ますます盛んとなり、摂関家・宮家・公家衆も参加して清涼殿あるいは小御所で、毎年行われるようになったのである。明治2年(1868)正月24日、京都御所の小御所で行われた和歌御会始も、以上のような伝統の上に行われたものであった。そして、この年の3月、明治天皇は東京に行幸され、以後、京都御所で和歌御会始が行われることはなかったのである(前掲「京都御所における和歌御会始」)。
3 歌会始の来歴(2)-東京における歌会始の展開
明治2年に東京に遷られた明治天皇は、翌年正月より、東京の皇居にて和歌御会始を行われた。京都の御所での多くの行事(例えば五節句)が、東京では継承されなかったことを考えると、明治天皇がいかに和歌を重んじられていたかがわかる。さらに明治7年(1893)には、従来の皇族・公卿・側近に加えて、一般国民にも詠進が認められ、天皇の叡覧に供されることとなり、明治12年(1898)には詠進歌のうち、特に優れたものが披講されることとなった。なお、この時期に洋装・立礼に改められたと推測されることとあわせて、現在の歌会始の原型はここに整備されたといえる(「歌会始とは」前掲『平成の宮中歌会始』)。そして明治19年(1905)には宮内省侍従職に御歌掛が設けられ(明治21年には宮内省御歌所に改組)、いわゆる歌会始を戦後まで担当することとなる。そして大正15年には『皇室典範』に基づく「皇室令」の一つとして「皇室儀制令」が制定され、その第五条に「講書始ノ式及歌會始ノ式ハ一月宮中ニ於テ之ヲ行フ」として、「歌会始」が規定されることとなる。
戦後の変動の中で、宮内省は宮内府を経て宮内庁となった。歌会始もこの前後に大きな変化が起こっている。まず昭和21年(1946)には歌会始を担っていた御歌所が廃止され、宮内府図書寮歌詠課が引き継いだが、それも翌年廃止され、結局、宮内府に歌会始詠進歌委員会が設置され、それが宮内庁歌会始委員会となって現在に至っている。
この変革の中で、詠進歌の選者も、従来の御歌所に所属する歌人から民間の歌人を選んで委嘱されることとなった。当時、侍従と図書寮歌詠課の課長を兼任しており、のちに長く侍従長を務めた入江相政(父は冷泉家出身で、御歌所課長を務めた入江為守)によれば、歌人で芸術院会員であった斎藤茂吉・窪田空穂・佐佐木信綱・千葉胤明に、従来の御歌所の寄人であった鳥野幸次を加えた5人というかたちをとった。正岡子規以降の近代短歌と、公家による堂上風に、江戸時代後期の香川景樹の流れをくむ桂園派を加えた「御歌所風」といわれた和歌の、いわば新旧の歌風の合同作業というかたちで行われたという。さらに和歌の「御題」も、従来の漢字数文字の「寒月照梅花」「暁山雲」から、より平易なものとして「あけぼの」が選ばれた。しかしまだ疎開先にいる選者もいて、なかなかその作業は難航したようである(入江相政「歌会始こぼれ話」入江相政ほか編『宮中新年歌会始 ご詠進の手引き』実業之日本社、岡野弘彦「宮中新年歌会始(一)」同『最後の弟子が語る折口信夫』平凡社)。
当時のことを記した『入江相政日記』には、選者が昭和天皇に拝謁したときのこととして、「お上より、歌道を通じて皇室と国民との結びつきに十分尽力してもらいたいといふ御言葉があつた由、一同非常に感激して居られた」(昭和21年10月7日、『入江相政日記』朝日文庫)という記述がある。入江氏はのちに、アメリカの記者から歌会始について質問を受けて回答したところ「なんとデモクラティックなことか」と感嘆されたという回想とともに、「全く、歌の道一筋で、皇室と国民は結びつけられる。歌さえすぐれていれば、ただそれだけでいいので、閲歴も境遇も、その他すべては、歌以外のことは、一切関係がないわけである」と記している(前掲「歌会始こぼれ話」)。
何度かの変遷を経ながらも、歌会始は、天皇・皇室と人々とを歌でつなぐという性格は維持され、強調されてきた。当初は戦国時代に行われた天皇と、周辺の公家のみが参加する行事だったものが、明治には一般国民にも広がり、さらに戦後は在外邦人の詠進が増加するなど、そのつながりは大きく、広くなっている。
今後もその結びつきを強め、広げるためにも、是非とも来年の歌会始には詠進を行ってもらいたいと思う。私(久禮)もここ数年、大学のゼミの学生諸君と、和歌の詠進を行っている。
詳細は宮内庁ホームページの「詠進要領」を参照されたい。来年の御題は「明」である。
※画像は『家庭十二ケ月』1月の巻,啓成社,明43. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/848315 (参照 2025-01-24)