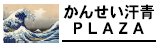近世尊王学者の「天子無姓」論
京都産業大学名誉教授 所 功
パソコン機能の進化はまことにありがたい。老々介護で外出を控えている私でも、最新のiPadでキーワード検索すれば、かなり多様な情報が得られる。
ただ、それが正しいとは限らないから、原典や論著などで確かめる必要がある。それは親しい友人にメールで頼むことが少なくない。そうして得た情報と検証に基づき、研究ノートや時事エッセイを、有縁の雑誌やHpなどに出している。
たとえば、「皇統」の本質論である。不思議なことに、皇統は男系男子のみという思い込みが、今や政府でも国会でも議論の前提となっている。それに対して私は、歴史を直視すれば、天皇(皇室)には一般氏族のような姓がなく、本来的に男系も女系もない(ただ男子の継承を優先して来た結果、振り返れば〝男系〟の如く見える。さりとて女子の継承も女帝の子の継承も、明治に至るまで法的に否定していたわけではない)と考える。
そこで、先賢の文献に例証がないか検索したところ、三例を見出すことができた。ひとつは、松下見林の代表著作である。見林(一六三七~一七〇四)は、漢学と和学を究め、東亜史上の日本を解明するため、三十年余りかけて中国と朝鮮の膨大な典籍から日本関係の記事を抄出し論評を加えた『異称日本伝』を元禄元年(一六八八)完成している。
その巻一(原漢文)に「本朝の風、天子は姓無し。天子の孫子は王氏を称す・・・およそ姓氏は人臣の例と為すなり。」とあり、天子(天皇)は姓が無く、姓も氏も人臣に通例のものと明言している。この見林は元禄九年(一六九六)『前王廟陵記』を著し、荒廃した陵墓研究の先鞭をつけた尊王学者である。
もう一つは、大窪詩仏(天民)の漢詩である。詩仏(一七六七~一八三七)は、詩文にも書画にも優れ、著名な漢詩「皇統歌」に、中国では周以来「幾姓氏相代」ってきたが、わが国では「大統長く相伝ふ。天子は姓氏無し。・・・天皇は日月の如し、万古変遷無し。・・・日出る国、自から綿々たり。」と彼我の異同を明瞭に表現している(安岡正篤氏著『名詩選釈』明徳出版社、昭和三十年など所収)。
いま一つは、幕末から明治にかけて豊田天功や栗田寛らにより完成された『大日本史』の「氏族志」にも「天子は姓無し、万世一統、天子すなはち事に因り命ずる(賜る)に氏姓を以てす。」と説明している。
これを要するに、日本の「天子(皇統)」には姓が無く、中国のような革命による易姓(王朝交替)も無い「万世一統」だから、父系を絶対視するような偏見も無い。従って、皇統の継承者は、皇祖皇宗の血縁を受け継ぐ皇族ならば男子でも女子でもよいことになる。 (令和七年六月十六日)