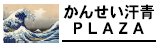無姓氏の皇室と同一称氏の家族こそ重要 京都産業大学名誉教授 所 功
いわゆる「男系女系」とか「夫婦別姓」という言葉は、人々に誤解と混乱を招きかねない。それゆえ、何度も論及してきたことながら、本来の基本概念を見直しておこう。
まず「男系女系」が問題になるのは、明治二十二年(一八八九)制定の「皇室典範」第一条に「大日本国皇位ハ、祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子、之ヲ継承ス」と明示され、それを戦後(昭和二十二年施行)の法律「皇室典範」第一条も、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と受け継いでいるからである。
しかし、現行の「皇統譜」によれば、第一代の神武天皇から第一二六代の今上陛下に至る「皇統」には、「姓」も「氏」も無い。皇族以外の一般臣民から入内した后妃も、生家の姓氏は解消され個人の「名」のみである。従って、「姓」の系統により「男系」とか「女系」というのであれば、皇統には男系も女系も本来ない。皇位継承者は「皇統に属し皇族の身分にあること」が不可欠の要件なのである。
ただ、皇位に即いて至高の政事・祭事(共にマツリゴト)を本務とする天皇の役割は、古代から男子のほうが担いやすいためか、大多数が代々「男子」の系統により受け継がれてきた。それが結果的に「男系」とみなされ、「皇統に属する男系の男子」を重視するに至ったのである。だから、これを長年の相対的な原則(例外あり)と言うことはできるが、永久の絶対的な原理(例外無し)とは断じえない。
それに対して、一般国民の有力者は、古代中国の影響を受けて五・六世紀ころから天皇より「姓氏」を賜った名家の子孫である。中国では皇帝も王侯も、男系(父系)の「姓」(血縁同族集団名)を絶対的な原理とし「同姓不始・異姓不養」を相対的な原則としてきた。それを儒教と共に受け容れた日本の豪族・貴族は、男系姓氏の継承を重視して、女性は結婚後も生家の姓氏を称し、夫と姓氏を別にする〝夫婦別姓〟を続けてきた。
やがて中世以降、公家も武家も「氏」本体から分岐した「家名・苗字」を称することが多い。その家でも慣習的に男性(夫)を家主(家長)としたが、例外的に女性(妻)も容認されたいる。さらに近代に入ると、明治四年(一八七一)姓氏の公称が廃止され、華族も平民も「苗字」のみで表示することになった。しかも同三十一年(一八八八)成立の旧「民法」七八八条で「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と定められたので、妻は夫の家名(苗字)を名乗ることが原則となったが、例外として「女戸主」も認められた。
それが戦後(昭和二十二年)成立の新「民法」七五〇条により「夫妻は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められた。つまり、新婚夫婦は夫か妻の「氏」(苗字)を選んで(生まれる子も)同一氏の家族を称することが原則となった。この夫妻(親子)同一称氏制度は、家族の一体性と連続性を保持するのに有効だと思われる。
ただ、実態としては、今なお妻が夫の氏を選ぶ夫妻が九〇%以上にのぼり、結婚後も生家の氏(いわゆる旧姓)を「通称」として公用できる道を拓くべきだ、という声が高い。その場合、生まれる子たちは、父か母と異なる氏にならざるをえない。
従って、「民法」の改定は、何が最も重要かを慎重に考えなければならない。その前提として、近代以降の法に存在しない「姓」と苗字の「氏」を混用して「夫婦別姓」などという誤称を止め、「家族同氏」の意義を再認識する必要があろう。
(令和七年五月三日稿)