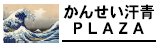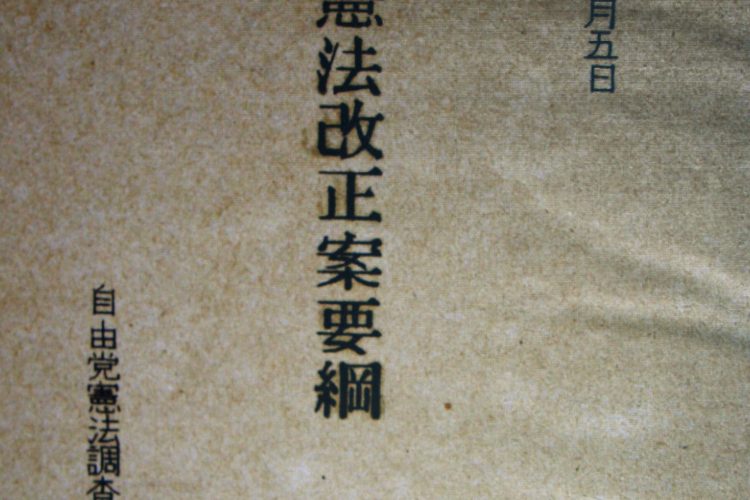真保守リーダーの憲法・典範改正案
京都産業大学名誉教授 所 功(83)
講和独立により始まった改正論議
わが国は八十年前の「終戦」(敗戦)から七年近く戦勝「連合国」の軍事占領を経て、「講和条約」の発効により主権を回復した。その意義は極めて大きい。
それによって、GHQの草案を基に作成された「日本国憲法」を自主的に改正しようとする論議が始まった。とりわけ昭和二十七年(一九五二)十月の総選挙で圧勝した「自由党」(総裁吉田茂氏)は、同二十九年三月「憲法調査会」を発足させた(同様に「改進党」でも「憲法調査会」を発足)。その主要課題は、新憲法の第二章「戦争放棄」を改正することにあり、同年六月「自衛隊法」と「防衛庁設置法」が可決公布されている。
とはいえ、当時の保守政党では、国柄の根本を表す第一章「天皇」の検討も行われ、具体的な改正案まで示されている。それが次第に議論されなくなり、専ら第九条の「解釈」と改正に関心が集中し、七十年後の今日に至っている。
自由党「憲法調査会」の「改正案要綱」
その「自由党憲法調査会」(会長岸信介氏)では、昭和二十九年十一月五日に『日本国憲法改正案要綱』を公表した(東京大学社会科学研究所架蔵本がネット公開されている)。この要綱では、まず「前文」について、「一、わが国が独立回復により、わが国の歴史と伝統を尊重し、国民の意思に基づき、自主的憲法を確立する旨を明らかにする。/二、国権は国民に発することを明かにし・・・福祉国家実現の理想を掲げる。/三、世界の平和、人類文化の発展に寄与せんとする国際協力の態度を宣明し・・・集団防衛体制に参加する旨を明らかにする」ことを明示している。
その上で、第一章の「天皇」について、「一、天皇は日本国の元首であって、国民の総意により国を代表するものとする。/二、天皇は内閣の進言に基づいて憲法に定める行為を行い、内閣がその責任を負うものとする。/三、天皇の行う行為に左の諸件を加える。⑴予算の公布/⑵国会の停会/⑶宣戦・講和の布告/⑷非常事態宣言及び緊急命令の公布/⑸条約の批准/⑹国務大臣及び法律に定めるその他の官吏の任命状、並びに大公使の信任状の受理/⑺外国大公使の信任状の受理/⑻大赦・特赦、減刑・刑の執行免除及び復権四、皇室財産の規定は法律(「皇室経済法」など)に拠る。
五、憲法改正の決議に「天皇の認証を要するものとする」と具体案を示したのである。
それのみならず、五の次に「附」として「皇室典範を改正し、女子の天皇を認めるものとし、その場合その配偶者(皇婿)は一代限り皇族待遇とする。但しその場合、摂政となることを得ないものとする」と明示するのみならず、その「説明書」で「皇位継承については、皇室典範第一条を改正し、皇男子なき場合は皇女子がこれを継ぐものとする。皇女子が皇位を継承する場合におけるその配偶者は一代限り皇族待遇を受けるものとし、摂政となることができないこととする」と、典範自体の改正案をはっきりと明示している(同三十年に中曽根康弘議員が纏めた「自主憲法の自主的性格」にも「皇室法の改正により、女子の天皇を認めるものとし、その場合、その配偶者は一代限り皇族待遇とする・・・」と、ほぼ同文がみえる)。
この「皇男子」「皇女子」は天皇(皇太子)と皇后(同妃)の間に生まれた「皇子」「皇女」(兄弟・姉妹を含む。皇次子以下の男女は含まない)を優先すると共に、「皇女子」も即位することができる「女子の天皇」を公認することによって可能になる〝直系継承〟を維持しようとしている。これは明治と戦後の典範が規制した「男系男子」限定主義の行き過ぎを克服することのできる画期的な改正案といえよう。
「女帝の制度を認める」案に多数賛同
それから一年後の昭和三十年(一九五五)十一月、自由党と日本民主党が「保守合同」して「自由民主党」が結成された(総裁鳩山一郎氏)。そこで、同三十二年六月成立の「憲法調査会法」に基づいて、翌年七月内閣に設けられた「憲法調査会」は、満七年間かけて憲法全般の問題点を調査検討した。その『憲法調査会報告書』(同三十九年七月提出。国立公文書館デジタルアーカイブに全文公開)は、膨大な量にのぼる。
その第二編「女帝の制度を認めるべきかどうか」をみると、反対より賛成の委員が多い。「女帝」を認める主な理由を抄出すれば、(1)「外国の例でも、女帝を認めるべきではないとする証拠はない」、(2)「日本において・・・古代には女帝の例があり、将来も天皇は男系の男子に限るべきかは問題である」、(3)「男系の男子の皇位継承者が絶える・・・稀有な場合も起こらないとは言えない」、(5)「憲法に男女同権の大原則が定められているにも拘わらず、皇室典範が女子の天皇を認めていないのは不当である」、(6)「天皇の国事行為が形式(儀礼)的なものに限られている以上は、皇婿(皇配)の問題(介入)も懸念する必要はない」、などの点をあげている。
ただ、女帝公認の賛成論者も、「憲法に明確にすべきである」という主張と、「憲法の規定は「皇統に属する者」とし、皇室典範では「男系の女子」にとどめるのが適当である」という意見に分かれている。とはいえ、多くの委員が「女帝(女子の天皇)」を成文化することに賛同していたことは確かである。
このように、かつての保守的な政党のリーダーたちは、古来の歴史をふまえ、明治以来の法制に再検討を加え、現在から将来を見通して、「皇男子が不在なら「皇女子」の皇位継承を公認する典範改正案を堂々と提示していた。これこそ〝真保守〟だと思われる。
「万世一系の天皇」は「皇統に属する皇族」から
ここにいう「保守」とは、本質的に重要なものを柔軟に保ち守っていく考え方・在り方であって、イデオロギッシュな「進歩主義」「革命主義」に対置される頑固な「保守主義」ではない。その「本質的に重要なもの」が何であるかは、さまざまな理解があって当然ながら、日本の国柄としては、千数百年以上の歴史を有する天皇(スメラミコト)が実在することにほかならない。
それゆえに、被占領下に制定された「日本国憲法」ですら、重要な第一章を「天皇」とし、その第一条に天皇は国家・国民統合の「象徴」、その第二条に「皇位は世襲のもの」と規定しているのである。
その「皇位は世襲」という憲法命題の具体策は、国会で定められた法律の「皇室典範」によって、継承者の資格や順序などを決めている。しかし、その新典範の大筋は、男尊女卑的な家父長制を前提とする明治の旧典範を踏襲したものであって、戦後数十年の間に皇室の実情とも社会の常識ともそぐわないようになってきた。
そこで、平成十年代に入り、政府内部で丹念な資料の収集と慎重な検討が行われ、小泉純一郎内閣(福田康夫官房長官)のもとで「皇室典範改正準備室」が設置された(現存)。そして同十七年(二〇〇五)有識者会議で議論を重ね、皇位継承者は「皇統に属する皇族」であれば、男女を問わず「長子優先」とし、皇族女子も結婚により宮家を創設しうる、という大胆な改正案を提示したのである。
それに対して、旧典範以来の「皇統に属する男系の男子」継承こそ絶対的な原理であり、皇族女子宮家の子孫が即位すれば、「女系」になる恐れがある、と信じ込んで声高に反対する人々が、熱烈に大小の集会を開いたり言論活動を繰り返してきた。その影響か、政府も政党の多くも「万世一系の天皇は男系の男子」のみ、というドグマに陥っているように見受けられる。
しかしながら、すでにこのホームページ(http://tokoroisao.jp/)でも説明してきたように(前回「無姓の皇室と同一称氏の家族こそ重要」など)、賜姓をする主体の天皇=天皇には俗姓(近代以降は名字)がないから、元来、「男系」も「女系」もない。
ただ、「皇統に属する男子」の天皇が多いため、それを振り返れば〝男系〟で続いてきたように見えるが、決して「皇統に属する女子」の天皇を否定したり排除するものではない。もし皇族女子が一般男性と結婚して宮家の当主になられても、その夫(皇婿)には世俗の名字が無くなるのである(皇族男子が一般女性と結婚される場合も、その妻(后妃)の名字は無くなるのと同様である)から、その子孫が万一即位されるようなことになっても、いわゆる〝女系〟にはならない。
端的にいえば、「万世一系の天皇」は「皇統に属する皇族の身分にある方」であることが本質的な要件にほかならない。けれども、歴史的に皇族男子が大多数であり、今後とも皇室で育たれた男子の方が皇位の重責を担って頂きやすい(女子には懐妊・出産が期待されるから容易ではない)と思われる。従って、皇位継承者は、単純な「長子優先」ではなく、皇族身分の「男子優先」とすることにした上で、万一に備えて「皇族女子」も即位しうる可能性を広げておくことが必要だと考えられる。
これこそが日本的な伝統に学びながら現状を克服して未来を拓く〝真保守〟の歩む道ではなかろうか。 (令和七年五月二十日稿)