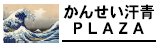皇位継承者は「皇統に属する皇族」が必須要件
(京都産業大学名誉教授)所 功
皇室制度の在り方を修正するための議論は、平成十年代から盛んになり、二十数年後の今も続いている。それに関心のある人々の大多数は、皇室を尊敬し永続を念願しているものとみられる。
ただ、ほとんどの論者は、皇室の伝統を尊重すると言いながら、古代以来の歴史を全体的に視る立場と、明治以降の法規を絶対視する立場とで、主張が著しく異る。私は前者に立っているが、政界や論壇などでは後者に立つ声が大きく、それを不動の原理と信じ込んでいる人も少くないようである。
そこで、実証的な研究者には、ほぼ自明のことながら、古代以来(旧「皇室典範」以前)の皇位継承有資格者に関する史実を簡単に確認しておこう(詳しくは後掲の著書などを参照して頂きたい)。
『日本書紀』に基づく「皇統譜」の皇祖神は女神
戦後(昭和二十二年)新「皇室典範」(法律)と共に定められた「皇統譜令」(政令)で再確定された「皇統譜」(宮内庁に原本所蔵。申請すれば閲覧可能)がある。これを拝見すると、まず「神代」として「天御中主神」から「伊弉諾神/伊弉冉神」に至り、その間に生まれられた「天照皇大神」の右脇に「世系第一」と記し、その御子孫として「皇統第一/世系第六」の「神武天皇」とそれ以下の歴代をあげている。
これは元正女帝の養老四年(七二〇)に撰上された正史『日本書紀』に基づいて「神代」の「世系」と人皇の「皇統」を一続きとしていることに特徴がある。それをどう解するかは様々ながら、「大日孁貴(おおひろめのむち)」(女神)とも称される「天照皇大神」が「世系第一」とされ、「皇祖神」として今なお伊勢の「皇大神宮」など全国に祀られている意味は大きい。
ただ、「神代」の伝承(神話)であるから、その御子孫と伝えられる「皇統第一」の神武天皇は「女系継承」だなどと強弁することは適切でない。大事なのは、人皇初代の神武天皇も歴代天皇も「天照皇大神」を皇祖神として仰ぎ祀られてきた確心的な繫がりが一貫していることである(それは生命を生み育てる母性を尊重する縄文時代以来の信仰が底流にあるのかもしれない)。
父系絶対の中国皇帝と「女帝」公認の日本
近代以前の中国では、父系で繫がる祖先を共有する父系血縁集団が「宗族」であり、各宗族の名称を「姓」という。「姓」を有する有力者が、争いに勝ち「天帝」の命を受けて選ばれたと称して王朝を開き、「皇帝」になる。その「父系男子孫」のみが祖先の祭祀と帝位を継承しうるとされてきたから、皇帝の女子が「女帝」(女皇)となることはなかった(「武」姓の則天は、「李」姓の高宗の皇后となり、まもなく強引に「聖神皇帝」となったが、皇后として葬られ、「則天武后」と称される)。
それに対してわが国では、およそ一世紀初めころ九州から東征して大和で拠点を築いた「皇統第一」神武天皇の子孫が、三世紀前半から四世紀前半ころまでに日本列島の諸豪族をほとんど勢力下に収め、五世紀には中国(南朝)に「倭国」の代表者として朝貢外交を展開しながら儒教などを採り入れた。
こうして格別な権威を確立した天皇(大王)は、比類のないオンリーワンの存在であり、五・六世紀ころから有力豪族などに職掌や地名にちなむ「氏」と、奉仕する王権での地位を表す「姓」を賜った。しかし、与える主体の天皇は氏も姓も必要とせず、その血縁子孫皇族に承け継がれてきた「万世一系の天皇」には臣民の「氏姓」(近代以降は名字)が無い。これこそ、わが皇室の本質的な特徴といえよう。
また、わが国の律令制度は、中国(主に隋・唐)のそれを手本として日本にふさわしく修訂を施した体系的な成文法である。そこに制定主体の天皇を規制する条文は殆ど無いが、皇族と臣民との関係に及ぶ規定はある。たとえば唐の「封爵令」を基にした日本(大宝・養老)の「継嗣令」冒頭に次のごとく見える(原漢文)。
およそ皇(天皇)の兄弟(姉妹)と皇子(皇女)、皆親王(内親王)と為よ〔女帝の
子も亦同じ〕。以外は並びに諸王(女王)と為よ。親王(内親王)より五世(来孫)、
王の名を得と雖も、皇親(皇室の親族)の限りに在らず。
※令文の表記は男性中心となっているが、女性の「姉妹及び皇女もこれに準ずる」(日
本思想大系『律令』「継嗣令」頭注)ので、それを丸括弧内に補った。
このうち原注の〔女帝の子、亦同じ〕は、本文と同等の法的効力を有するが、唐(開元令など)の「封爵令」にはない日本独自の規定である。つまり中国では「女帝」を否定しているから必要ないが、「女帝」を公認する日本では、「古記」(『令集解』所引の「大宝令」注釈書)のごとく、「女帝の子、亦同じ」というのは、女帝となる娘の父が「諸王」であっても、娘が即位すれば諸王から「親王」となり、「女帝の兄弟(姉妹)も男帝の兄弟(姉妹)と一種(同様)なり」と原注を加える必要があったのである。
その女帝は、すでに六世紀末に始まり、飛鳥・奈良時代(ほぼ七・八世紀)に相つぎ、江戸時代の二例を含めて八方十代(二方は二度即位)にのぼる。ただ、継嗣令に「女帝の子」というのは、女帝が結婚(ないし再婚)して生まれる子(男女)を想定していたことになるが、その実例はほとんどない。
「天つ日嗣には必ず皇緒を立てよ」
このように、わが国では「男帝」だけでなく「女帝」も公認されていた。とはいえ、武力抗争に勝利して国内の統合発展を指導する大王(のち天皇)には、皇族中の男子がふさわしいと考えられたのか、ほぼ一世紀から六世紀ころまでは、すべて男性の「皇孫命」(すめみまのみこと)が皇位を担ってきた。
しかし、㉙欽明天皇(在位五三九~五七一)が、有力豪族の蘇我氏と関係を深められたところ、それで専横を極めた蘇我氏が㉜崇峻天皇を暗殺するに至った。そこで、非常事態を救い皇室に安定をもたらすため、諸臣が協議を重ねた結果、㉚敏達天皇の皇后(寡婦)を㉝推古天皇として擁立した(在位五九二~六二八)。これは日本だけでなく中国にも朝鮮諸国にも前例のない、東アジア世界で初めての女帝であるが、三十数年にわたって治績をあげられており、決して単なる中継ぎではない。
同様に飛鳥・奈良時代(ほぼ七世紀)には六方八代の女帝が相次いでいる。ただ、その最後の㊽称徳天皇(在位七六四~七七〇)は、独身であり仏教に熱心なあまり、看病僧を務めた弓削(ゆげ)道鏡を重用して「太政大臣禅師」「法王」にまで取り立てられた。それを見て神護景雲三年(七六九)、道鏡の弟が宇佐八幡の神官と結んで道鏡を皇位に即けようと企策した。しかし、真相を確かめるため宇佐へ遣わされた和気清麻呂(七三三~七九九、称徳女帝の側近女官和気広虫の弟)は、あらためて八幡大神の神託をえて帰京し、次のごとく復奏している(丸括弧内私注)。
我が国家(みかど)、開闢(有史)以来、君と臣(の分)定まりぬ。臣を以て君と為すこと、未
だ有らず。天つ日嗣(天皇の地位)には皇(こう)緒(ちょ)(皇族の継嗣)を立てよ。無道の人(道鏡)は早く掃ひ除くべし。
すなわち、皇位継承の有資格者は、神武天皇の血縁子孫で皇族身分に在る者でなければならない(本来男女を問わない)が、それは「君と臣の分(区別)」こそ重要なことを意味する。念のため、58光孝天皇の皇子の59宇多天皇は、父帝が太政大臣藤原基経への配慮から他の皇子・皇女と共に一たん源朝臣を下賜されて、暫く臣籍にあったが、三年後臨終間際の父帝の切望により、皇籍に復して即位された。しかし、これは特殊なケースであり、単純に君臣の分を乱したとはいえない。
継承皇族を「男系の男子」に限るのは無理
以上を要するに、㈠皇位継承者は元来「皇統に属する皇族」であることが本質的に重要であり、㈡それには皇室に生まれ育った男系男子だけでなく、皇族女子も含まれている。㈢中国の皇帝は「姓」をもち男系(父系)を絶対視するから「男帝」しか存在しないが、㈣日本の皇室には氏も姓も無く、律令法では「女帝」も公認されている。㈤その皇位継承者は皇室で生まれ育たれた皇族でなければならない。㈥それは男女を問わないけれども、男子皇族のほうが皇位を担いやすいため「男帝」が多いので、結果的に〝男系〟で続いてきたように見られやすい。
ところが、明治二十二年(一八八九)制定の旧「皇室典範」以来、皇位継承者を皇統に属する「男系の男子」に限定してしまった。しかも、昭和二十二年(一九四七)施行の新「皇室典範」では、それを引き継ぐのみならず、旧典範で容認されていた側室所生の庶子を否定している。古来多く(半数近く)皇族男子により皇位を継承できたのは、側室を是認してきたからであるが、それは今や通用しない。
しかしながら、一夫一婦制のもとで「男系の男子」のみにより皇位を継承し続けていくことは、極めて困難であり、皇室の方々に無理な重圧を強いているといわざるをえない。現に今上陛下は、雅子皇后と結婚されてから八年目に敬宮愛子内親王が誕生されたけれども、男子(親王)でないから駄目という烙印を押され、雅子さまが精神的に傷ついて病気になられたことは、まことに痛ましい。
ちなみに、戦後(昭和二十二年十月)皇籍を離れた十一宮家では、皇室に準じて男系男子限定を墨守するうちに男性当主を得られず、すでに大半が相続不能となっている(若い男子孫がいるのは四家のみ)。
従って、今後の在り方としては、歴史的に多い皇族男子を優先するにせよ、皇族女子も公認しておく必要があろう。「皇位は世襲」という憲法の命題は「皇統第一/神武天皇」以来の血縁子孫皇族が、皇室で生まれ育ち品位と徳望を身に付けて天皇の重責を担われることであって、それを男子に限定し女子を排除するようなことではない。
(令和七年五月二十日稿)
〈参考拙著〉『皇位継承のあり方』(平成18年、PHP新書)、『皇室典範と女性宮家』(平成24年、勉誠出版)、『象徴天皇〝高齢譲位〟の真相』(平成29年、ベスト新書)、『「皇族の確保」急務所見』(令和6年、方丈堂出版)