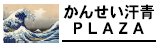「皇室典範」の改正試案を実現する具体策
京都産業大学名誉教授 所 功
この一年間、皇室に関しても、様々な難しい問題点が浮き彫りとなり、その永続に資する「皇室典範」改正は遅々として進まない。
そこで、来年こそは典範改正を一部分でも実現してほしい、という切なる願いをこめて、僭越ながら平成二十五年(二〇一三)に作成した「皇室典範」の改正試案を、ここに再提示して、参考に供したい。
これは十数年前から現行憲法の改正論議が盛んになり、とりわけ自由民主党も産経新聞社も、具体的な改正案を公表した。その大半は妥当な案だと認められるが、なお検討の余地があると思われた。
そんな折に、大阪の国民会館から講演の依頼を受けたので、「日本国憲法の『天皇』をマトモに議論しよう」と題して管見を述べた。また、その全容を同館の叢書として出版する際『日本国憲法「天皇」の再検討』と題し、自民案と産経案と管見案との対比も付載するのみならず、憲法と一体の「皇室典範」についても独自の「改正試案」を併載した。
この冊子(A5判一〇〇頁、頒価五百円)は、まだ若干残部がある由にて、関心のある方は国民会館(FAX〇六ー六九四一ー二四三五、http:kokuminkaikan.jp)に問い合わせて頂きたいが、ここに付一と付二の全文を添付するので、ぜひ御一覧賜りたい。
「皇室典範」第九条の改正試案
このうち、付一は別の機会に解説するとして、今回は付二のなかでも当面題題となっている「皇族の確保」に直接関係する第九条と第十二条に関してのみ説明を加えよう(念のため、第四条は従来どおりとしていたが、平成二十六年制定の「皇室典範特例法」により、「天皇が崩じたとき、ないし高齢を理由に退位(譲位)するときは、皇嗣が直ちに即位する」と改める)。
まず現行の第九条では、「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と定められ、皇室に養子を迎えることも皇室から養子を出すこともできない。これは、明治の「皇室典範」により、明治の初めから一代限りで次々創立されてきた宮家(すべて伏見宮系)が永世に続きうる世襲宮家とされ、皇族数が段々増大し国費の負担も過重になるため、制限を加えることにしたのであろう。それが戦後の典範に引き継がれたのである。
しかし、GHQの皇室弱体化政策により、新典範の施行半年後(昭和二十二年十月)、直宮(じきみや)三家以外の伏見宮系十一宮家は全員(男性二十六名、女性二十五名)、皇籍を離れ一般国民にされ、皇族数が激減するに至った。従って、それを不当と考えれば、五年後(同二十七年四月)の講和独立時早々に皇籍への復帰をはかるべきところ、何の手も打たれていない。
その結果、半世紀以上経った今日、旧十一宮家は次々絶家となり、他の数家も皇室に倣って「男系の男子」による相続は困難な状況にある。それでも残る四家には一般国民として生まれ育った男子が実在する。この点に注目して、その中から皇族となるにふさわしい人を見つけ、皇室に養子として入れる道を開こうとするのが、一昨年末の政府案である。
現在、そのような適任者がいるとしても、当家・当人が諒解されるかどうか判らないが、それを可能とするには、典範第九条を改正しなければならない。そのため試案では、現行文を原則的に残しながら、例外的に「養子をすることができる」としたのである。
ただ、その養子としては、政府案のように旧宮家の男系男子孫に限るのか、それ以外に「皇統に属する皇族」の男系子孫、たとえば近世以降の皇別摂家(近衛、鷹司三家)子孫や、戦前に臣籍降下した旧華族の男子孫(数家あり)なども含むのか。また、その該当者は皇族の身分を取得してから婚姻するのか、結婚により皇族となるのか(後者であれば、後述の第十二条と同趣)。さらに、その養子を受け入れる皇室(内廷・宮家)の希望・内諾がなければ成り立たないが、それをどのように表明されるようにすることが適切か。いろいろ慎重に検討しておくべきことが多く、それらを「施行細則」に定めなければならない。そうであれば、相当な時間を要することになろう。
「皇室典範」第十二条の改正試案
つぎに現行の第十二条では、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定められ、皇族女子(内親王・女王)が一般男性と結婚すれば、皇族の身分を失い一般国民とならなければならない。
これは、明治の典範第一条で、皇位継承者は、「祖宗の皇統にして男系男子」と限定する反面、第四十四条で、「皇族女子の臣籍に嫁したる者は皇族の列(身分)に在らず」と定めていた。それが戦後の典範に受け継がれたのである。
しかし、皇室で生まれ育った女性(内親王・女王)は、結婚により皇室へ入った皇后・皇太子妃・親王妃・王妃と共に、皇族として各々公的な役割を戦前から果たされ、戦後も、皇室と国民を結ぶ公務を担っておられる意義は大きい。それが第十一条を放置すれば、皇族数の減少を止められず、公務の分担も困難になろう。
そこで、第十一条を改めて「皇族(女子)は、皇族以外の者(男性)と婚姻したときも、皇室会議の議を経て、皇族の身分に留まることができる」という試案を考えたのである。これは従来のごとく皇族男子が一般女性と結婚すれば、皇族身分の宮家当主となり、その女性も皇族となれるように、皇族女子が一般男性と結婚しても、皇族身分のまま新宮家の当主となり、その男性も皇族となれるようにする道を開くことである。これが実現しても、第一条を改正しない限り、皇族女子宮家に皇位継承資格は生じえない。
ただ、その皇室に入る一般男性は、一般女性と同様に、皇族となるにふさわしい方を厳選して、皇室会議の議で承認を得なければならないことを要件とする。また、現行典範のもとで生まれ育たれた現在の皇族女子には、皇室の身分を離れる選択の余地も残しておく必要があると思われる。その上で、前例のない皇族女子の夫と子孫の具体的な在り方などは、慎重に検討して「施行細則」に定めなければならないが、それにも相当の時間がいるであろう。
従って、当面は政府案のうち、国会の与野党で合意の可能な大筋のみで典範改正の第一歩を踏み出し、その「施行細則」を約一年以内に作成するような手順が必要だと思われる。
目的は皇室の永続に役立つ制度を整えることである。その目標に向けて、長い皇室史に学びながら、変化する現状を直視して、徐々に改良を重ねてゆく努力を続けたい。 (令和六年十二月三十日記)
国民会館叢書『日本国憲法「天皇」の改正』 日本国憲法「天皇」の改正